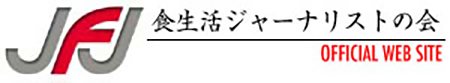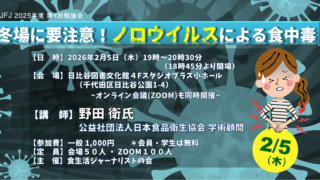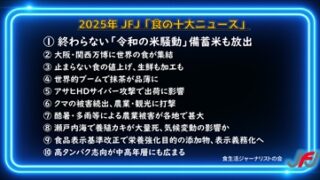・講 師:木村滋子さん(食生活ジャーナリスト・JFJ会員)
ディスカッション進行:大久保朱夏さん(食ジャーナリスト・JFJ幹事)
・会 場:東京ウィメンズプラザ視聴覚室(渋谷区神宮前5-53-67)
・参加者:37名
・文 責:田尻 泉
2018年7月19日、食生活ジャーナリスト木村滋子さんを講師に迎え、料理の療法としての可能性を考える勉強会を開催しました。
木村さんは、国内外での様々な体験や長年の栄養士としての経験を経て料理の療法としての可能性に注目し、その効果の科学的検証に取りみました。

木村さんの講義の要旨は以下の通りです。
きっかけは精神障害のある人の自立支援のための調理実習の講師を担当したことでした。コミュニケーションが難しい人が笑顔になったり、会話がはずんだりなどの影響が認められましたが、それらをより効果的に活かす方法は検証されていませんでした。また、社会福祉学、心理学、医学、調理学などそれぞれの分野の専門家はいても、分野の垣根を超えて「料理」を「療法」としてとらえる見地もありませんでした。「料理」の精神面における影響を検証した先行研究はありましたが、それらは「共同作業」や「共食」などによる効果も含めた心理的変化をとらえており、「料理」の個々の作業がもつ効果を客観的に検証するものではありませんでした。
そこで、試行錯誤を繰り返しながら、11年かけて作業ごとの効果の検証を試みました。具体的には、「切る」という作業と「こねる」という作業がそれぞれもたらす効果とその違いを分析しました。結果として、どちらも作業をする人の不安と気分の改善に効果があること、さらに、「道具をつかって切る」場合と「直接食材に触れてこねる」場合では:それぞれ異なる影響が得られることが確認できました。それにより、作業ごとの特性の違いを考えて組み立てることで、料理療法の効果はもっと広がることを確信しました。
潜在的に「料理」を「療法」として活用している場は既に多くあります。しかしながら「療法」としての効果が検証されておらず、またその効果が論理的に認識されていないため、せっかく「料理」を取り入れても効果的な実践に結びついていないのが実情です。
基礎研究によってエビデンスを蓄積し、「料理療法」という概念を体系的に構築し普及することが効果的な実践のための今後の課題です。また、実践例を収集や「料理療法士」などの専門家の育成、関連分野の専門家との連携も必要だと考えています。
木村さんの講演に続いて、参加者全員で料理療法の可能性についてディスカッションを行いました。それに先立ち、ディスカッションの進行を務めた大久保朱夏さんが、デイサービスに料理を取り入れている例を紹介しました。

大久保さんが取材をした施設では、要介護2で認知症の傾向がある人が料理に取り組みます。自分達で目標を立て、自分ができる範囲の様々な作業をすることで、自分で色々と考える様になり、食欲がわき、顔が生き生きとするなどの変化がみられるそうです。また、料理をすることが家に帰ってからの家族との会話にもつながっています。
ディスカッションはグループに分かれて行われ、活発な議論が交わされました。

料理療法の可能性に期待する意見も多く、料理は作るという行為だけでなく最後に三大欲求の一つである「食べる」という行為があるというところが他の療法と違うのでは、あるいは、五感を全て使って取り組む料理は最も優位性が高いのではないか、実践例やエビデンスがさらに蓄積されていけば行政も動かしやすくなるのでは、などの声がありました。
料理療法の効果測定の懸念として、対象者や評価ポイントの設定が難しいことや、料理には複数の作業や人、食べるという行為など多くの要素が絡むので個々の要素の効果は特定しにくいのではという意見もありました。また、料理自体にトラウマがある人へのアプローチをどうするかという課題も挙げられました。
JFJのメインテーマである「食と生活」に密着している「料理」の「療法」としての可能性を議論する有意義な勉強会となりました。