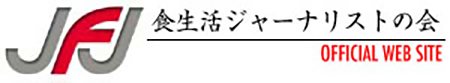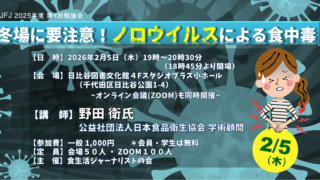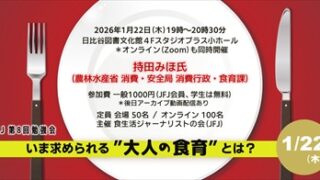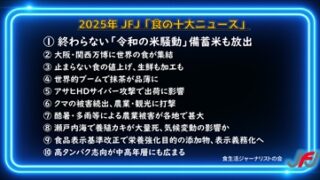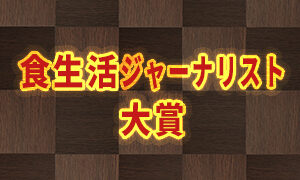・演 題:土を知ることで解決する食の問題とはーー土の研究者が展望する未来の農業
・日 時:2025年3月24日(月)19時~20時30分
・講 師:藤井 一至/土の研究者
・進 行:中野栄子
・参加者:会場参加23名、オンライン参加63名
・文 責:中野栄子
**************

土は食の95~98%を生み出す重要な生産基盤であるが、日本では自分で求めない限り、土について学ぶ機会はほぼない。土壌劣化を防ぐ不耕起栽培などの農法、健康や食についての問題、また、食料安全保障、みどりの食料システム戦略、給食有機化といった政策に対して向けられる不安や失望は、土への理解不足が原因となっていることも少なくない。土とは何か、日本の土、世界の土はどのような特徴があるのかーー。地球の過酷な環境下のあらゆる土を知り尽くし、研究を重ねる“土の研究者”の藤井一至氏に、土について語ってもらい、日本の農業の未来を展望してもらった。
……………………………………………………………………………………………………
今なぜ、土なのかーー。藤井氏は講演冒頭にこう問いかけた。公害問題のように、経済発展と自然保護は長く対立構造をとってきた。しかし、生物多様性、生態系サービス、SDGsというコンセプトの登場によって歩み寄りが見られ、企業は「開発ばっかりやっていると資源なくなるぞ」「投資家から見放されるぞ」「コンプライアンスちゃんとしろ」と言われるようになり、社会全体としても自然、気候、生物、環境に向き合うようになりつつある。そんな中で、生態系や食料生産の基盤である土壌を理解する重要性が語られた。
そもそも、私たちの食べ物は、その土地の気候と土に大きく左右されている。食文化は土によって制約を受けているといっても過言ではない。そんな中、日本は世界的に見ても決して良いとはいえない土によって、世界に誇る日本食文化を作り上げてきた。その一つ、稲作も昨今、状況が変わってきた。水田稲作から畑地水稲栽培に切り替えを検討する農家も増えている。というのも、メタンガスが発生する水田は地球温暖化防止の観点で逆風下におかれ、用水確保が難しい地域も多い。日本は水田農業の維持に年間6000億円のコストをかけており、用水路の整備事業は高齢化が進む農村において労働力とコストの面で年々難しくなっている。
土壌学は従来、水田稲作を称賛してきた。田んぼの良さは、連作障害が起こらず、雑草管理もしやすいこと。輪作でコムギやダイズを栽培するにしても、これらは世界的にみると日本は生産性が低いといわれている。いろいろな営農のオプションを用意しておくことが、日本のこれからの農業経営に役立つ。それは「経営が持続しないと土も持続できない」からだ。その日本の土は、「世界一とは言わないが、水も豊富にあり、ぼちぼち良い感じ」という。「その土のお陰で日本は世界の中でも農業が継続できている素晴らしい国であることを認識し、自覚すべきだ」とも藤井氏は語った。
慣行栽培で肥料を施すと、アフリカでは作物に栄養が届くのが約90%であるのに対し、日本では約40%と言われている。この違いは何なのか。作物には、菌根菌や根粒菌といった共生微生物がつくが、これは化学肥料と同じような働きをする。栄養が足りなければ共生微生物は頑張るが、化学肥料が施されると共生微生物は“スネ”て働かなくなる。米国では共生微生物をゲノム編集することによって、化学肥料の施肥量を大幅に減らす技術も開発されている。
農地における土を巡っては、有機栽培と慣行栽培の対立が続いている。有機栽培支持派は有機栽培を土が生きる環境保全だとし、慣行栽培に対しては土が死ぬ環境破壊と断じている。藤井氏はこうした対立が起こらないよう配慮すべしと唱える。というのも、それぞれの栽培法には一長一短があり、栽培の成否は土次第だからだ。ブータンでは有機栽培が成功し、スリランカでは失敗しているのは、知見の集積などの準備が違ったから。また、有機栽培が科学的に環境に優しくはない面もあると指摘する。EUでは有機肥料の施肥量に上限値を設定しているが、日本にはない。環境に優しいと言うためには、上限値などルールを作っていかなければならないと藤井氏は訴えた。
もう一つ、有機農産物については、“そのマーケットがあるのかという問題”を藤井氏は指摘する。昨今のコメやキャベツの値上がりで、日本人は食べ物に対してお金を渋る面があることが分かってきて、農家の悩みの種となっている。一般的にコストがかかる有機農産物は高価であり、日本では有機農産物にかける支出が少なすぎる。
給食有機化問題についても言及した。安全安心な食べ物を子どもたちに提供すると動きにおいては、科学的エビデンスが十分でない今、子どもたちに間違った印象を植え付けることになる。無理矢理感はあるが、有機という新しいマーケットの拡大のために給食に取り入れることは、まだ理解できる。親の収入によって子供がありつけるかどうかが決まってしまっている。したがって、親の収入に左右されない給食という場で、ある一定の割合で有機農産物を使うことには意義があるとした。

最後に、藤井氏は「完璧な農法はない」と主張。気候と品種と土を考えて、どれが大切かを見極めることが必要だと言う。続けて、「日本の土も、酸性、黒ボク土と問題があることも事実。しかし、肥沃な土地でなくとも、ありのままの土は十分魅力的である。日本はこの魅力を生かした農業を目指すべきではないか」と結んだ。