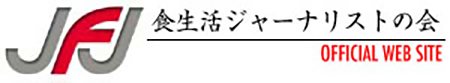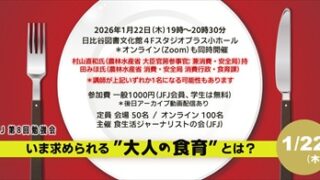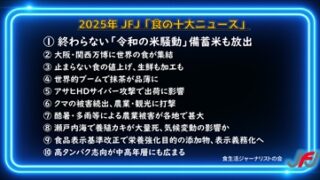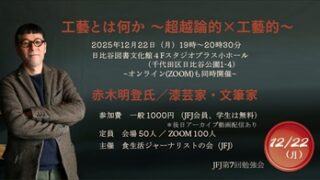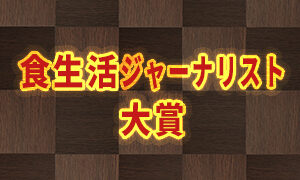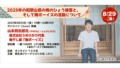・演 題:なぜ私はジャーナリストとして「海の危機」をテーマに活動しているのか。
・日 時:2025年7月28日(月)19時~20時30分
・講 師:佐々木ひろこ(一般社団法人Chefs for the Blue代表理事)
・進 行:小山伸二
・参加者:会場参加15名、オンライン参加34名
・文 責:小山伸二
**************

第3回の勉強会は、「海の危機」をテーマにフードジャーナリストの活動をされている佐々木ひろこさんを講師にお迎えした。
フードジャーナリストとして、レストランをはじめ食の現場の取材などを通して長年、「おいしさ」を伝えてきた佐々木さん。
20年以上のキャリアのなかで、あるとき、水産現場での取材機会を得たことが転機となって、水産業の課題、海の危機について、学ぶことになったそうだ。
その取材を通して、水産業の課題、深刻な「海の危機」について自分があまりに無知だったこと。そして、「海の危機」を読者に伝えてこなかったことに思い至り、自責の念にかられた、と。
それから佐々木さんは、水産業の現場に頻繁に足を運び、水産関連の論文や資料にあたり、さらに、自分と同様に深刻な「海の現状」について知らなかったレストランのシェフたちと勉強会を立ち上げ、現在の「一般社団法人Chefs for the Blue」設立にいたる経緯をお話いただいた。
「みなさんは、ご存知でしたか?」
そんな問いかけから、参加者のために、現状の海の課題、水産資源の現状についての基本情報を解説していただきました。
本来は魚介類が豊富な日本では魚食が食文化の根幹をなし、郷土料理の多くを支えてきた。
その漁獲量が激減している実態。
1995年と2020年を比較して、さけ類が20%、さんまが10%、くるまえびが9%、するめいかが17%へと激減している。つまりこの35年で漁獲量が5分の1、10分の1に激減している。
戦後続いた国土開発の影響、海の再生産能力を超えた漁獲、化学物質・ゴミ等の汚染、プランクトンなどの餌不足、他国の公海での漁獲、温暖化による影響、海水の酸性化など、激減の理由には複数の要因が複合的にからんでいると考えられている。
このまま放置していたら、豊かな日本の魚食文化が滅びてしまうかもしれない。
もう時間が、あまり残されていないのではないか。
こうした危機感のもと、フードジャーナリストとしてできることは何かを考えた佐々木さん。
そこで、長年取材を重ねてきた「発信力」を持っている料理人たちを巻き込み、連携することで、より早く、より多くのひとに伝える必要がある、と「Chefs for the Blue」を立ち上げることにした、と。
料理人たちは、生産者と消費者の間に居て、この両者をつなぐ場所にいるのではないか。
現在、45人のメンバーが積極的に情報発信しているそうだ。料理人が食をめぐる社会課題の解決に取り組む姿は世界各地で見られる現象でもある。
現在、「Chefs for the Blue」では、政府に対して持続可能な水産資源のための政策提言や、一般向けの啓蒙イベント、大学生・専門学校生などを対象にした教育プログラムの開発など多方面に渡って、活動されている。
水産資源についての調査、資料など、陸上の農業などと比べても、非常に難しい面がある。また、水産業界独自の仕組みや、日本中にある水産現場の事情はそれぞれに異なり、課題解決は一筋縄ではいかない。
ただ、食をテーマに活動しているJFJ会員のひとりひとりも、「海の危機」を自分ごとにして、学び、考え、伝えることの重要性を、佐々木さんに教えていただいた。