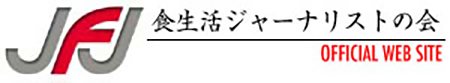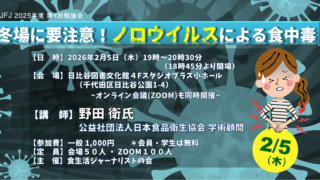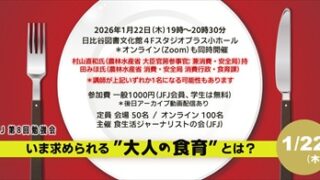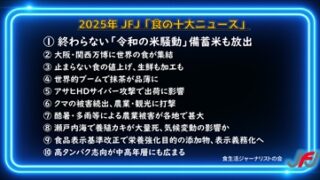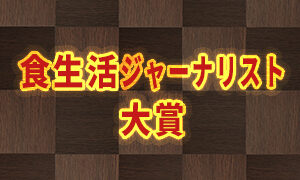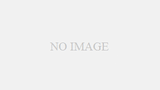企画の詳細が決定しました。
会員のみなさんで近畿圏在住の知り合いのジャーナリスト、メディア関係者にお声掛け下さい。
主催:食生活ジャーナリストの会
http://www.jfj-net.com/
協力:辻調理師専門学校
http://www.tsujicho.com/
会場:辻調理師専門学校 視聴覚室
大阪市阿倍野区松崎町3-16-11
http://www.tsuji.ac.jp/access/(地図①)
日 時:9月28日(水) 開場:17時30分/開演:18時00分
参加費:JFJ会員・一般ともに無料
定 員:100名
《企画趣旨》
JFJ の設立後四半世紀が経ち、食をめぐるメディア、ジャーナリズムの
世界にもさまざまな課題、問題があります。健康食品や食品表示をめぐ
る問題に代表されるように、今日、食の報道には、きわめて高度な知識、
見識が求められています。
ともすれば、メディア自身が「食の偽情報」に加担するリスクも指摘さ
れます。社会構造の変化とともに混迷をきわめる食の状況。構造的な問
題を抱える農業、漁業、畜産業などから食品加工業、飲食業界にいたる
まで、ひろくジャンルを超えた意見交換や、知見がいまほど必要とされ
ているときはありません。
JFJ では、東京だけではなく、広く全国各地で食のジャーナリズムの現
場で活動されている方々に参集していただき、さまざまな勉強と交流の
場を提供していきたいと考えています。
今回、関西地区を中心にして、大阪市にある辻調理師専門学校の協力を
得て、食をめぐるメディア人、研究者をはじめ広く「食」の専門家に参
集いただき、JFJ 西日本支部の立ち上げに向けたイベントとして開催す
ることになりました。
①JFJ代表幹事挨拶 18時~18時20分
小島正美さん(毎日新聞・生活報道部編集委員)
JFJのこれまでの歩みとこれからの展開
②在関西のメディア人によるクロストーク 18時20分~19時00分
~関西の食のメディアの現状と展望~
進行:門上武司さん(フードコラムニスト、JFJ会員)
本郷義浩さん(毎日放送・プロデューサー)
中本由美子さん(「あまから手帖」編集長)
長友麻希子さん(フリーライター)
新聞関係者:調整中
③「食べる通信」編集長トークセッション 19時00分~19時45分
進行:小山伸二(JFJ副代表幹事、辻調理師専門学校メディア・プロデューサー)
~新しい食のメディアの誕生。創刊の経緯から現状、そして未来~
『兵庫食べる通信』編集長・光岡大介さん
『奈良食べる通信』編集長・福吉貴英さん
『伊勢志摩食べる通信』編集長・竹内千尋さん
『つくりびと – 食べる通信 from おおさか -』編集長・山口沙弥佳さん
『京都食べる通信』編集長・大西梨加さん
④参加者との質疑応答 19時45分~20時00分