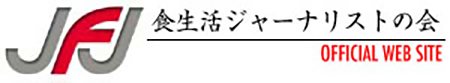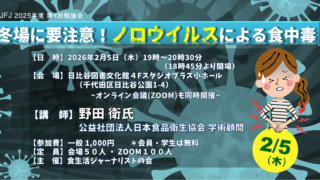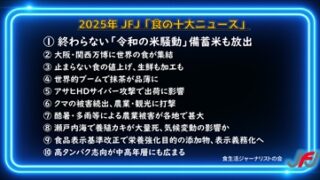・講 師:藤原辰史 氏(京都大学人文科学研究所准教授)農業思想史
・会 場:東京ウィメンズプラザ(表参道)1階 視聴覚室
・参加者:28名
・文 責:小山伸二
昨年度の西日本支部での勉強会にひきつづき、京都大学の藤原辰史先生をお迎えしての勉強会。
テーマは、「食と農から考える人類の未来」でした。
藤原さんは、農業史研究者として、独自の視点から20世紀の歴史、農業、食を考察し、『ナチスのキッチン』、『戦争と農業』、『トラクターの世界史』などの著作で注目を浴びている新進気鋭の歴史学者。
今回は、そんな「藤原史観」から人類の食の未来を語っていただきました。
■「食」をめぐる三つの未来像
考えられる食の未来像として3つの図版が提示され、食「文化」の不在の未来像の不気味さについての話が始まった。
まず、ネットでも話題になった「三等階級国民食」と名付けられたディストピア食。
コンビニで売られている機能性食品、サプリメント、スナック菓子だけで構成されたランチボックス。すでに食が、ただ空腹をみたすためだけものになってしまう「未来」が現在進行形なのかもしれないという指摘。
2つ目は、画家の石田徹也が描いたガソリンスタンドのようなカウンターで、まるで自動車の給油のように食べ物を流し込まれる男たちの絵。人間が食事を摂る行為が、自動車の給油と同じだというのは、実は、すでにファストフード店あたりの光景にかさなるのではないか。
そして、3つ目は、SF小説『ねじまき少女』(パオロ・バチガルピ著)で描かれた、エネルギーと食糧(遺伝子組み換え植物の種子)の独占企業が世界を支配する世界。文化としての多様性を奪われたディストピア小説。
以上の3つに共通する暗い人類の食をめぐる未来は、「食」の工業化、画一化、脱「文化」化が、すでに現在進行形なのではないかという危機意識を強くわれわれに教えてくれる。そういう意味で、研究者として、そうではない「もうひとつの世界」を構想するために、研究と行動が求められている、という自らのスタンスを明確にした上で、3冊の本の紹介に(彼の大学での授業では、さかんに本を紹介することで受講者の自発的な学びをうながす手法をとっているそうだ)。
■歴史的な背景をさぐる
食と農の未来を考えるうえで、いま読むべき3冊の本を紹介。
①『戦争がつくった現代の食卓』(アナスタシア・マークス・デ・サルセド著/白揚社)は、アメリカ陸軍の食糧(レーション)の開発から20世紀のさまざまな加工食品が生み出された実態をレポートした問題作。戦争という非日常での食べ物が、ごくありふれた日常の食べ物になっている実態が明らかにされる。
②『モンサント』(マリー=モニク・ロバン著/作品社)は、世界の農業に大きな影響力を持つバイオ化学企業、モンサントをめぐる話。ベトナム戦争時代に枯れ葉剤を作ったことで知られるこの大企業の遺伝子組み換えなどテクノロジーがもたらす世界を紹介。単に、人間に害があるかないかだけではとらえられない、食と生態系についての視点が必要だという指摘。
③『世界からバナナがなくなるまえに』(ロブ・ダン著/青土社)は、20世紀の農業が人口爆発に対応するための大量生産にシフトすることで拡大した農薬と化学肥料の使用と、作物品種の画一化が、いまなお根強く、進行していることに警鐘を鳴らしている著作。
この3冊を通して、現在進行形の「食」をめぐる諸問題を、単に「現在」の人間の体に良い悪いか、餌としての食糧供給システムさえ確立すればいいという観点ではなく、「未来」を見据えた生態系的な意識、持続可能な地球規模の文明論的な視野を持つ必要性がある、と。
■考えられる未来
これからの時代、ますます食事は合理化、軍隊化、画一化、簡便化、工業化していくだろう。そのことに少しでも歯止めをかけるためにも、各地域に残された在来作物の保全や大手種子メーカーに頼らない種子の保全のような活動は重要になる。さらには、経済原理最優先の社会を変えるためにも、食文化の未来は、現状のままでは、まさにディストピア小説の世界そのものなるという危機感を、多くのひとが共有すべきである。
そのために、食にかかわるそれぞれの立場のひとたち(生産者、加工、流通、小売り、外食/給食、研究者、教育機関、行政)が、自分のできるところから考え、連携し、行動する必要がある。
地域が抱える食の問題を、単なる自己責任論的に閉じられた個々の家庭や個人の問題にするのではなく、「公衆食堂」のような概念をも構想しながら、新しいコミュニティの場所としての「食事の場所」の創出を考えるべきではないか。
■考察
最後に、いま執筆中の「学校給食」について。これからの社会のなかでの食を考えたときに、給食という食事の場所の再発見と再構築が求められているのではないか、という問題提起を。このテーマについては、11月に『給食の歴史』というタイトルで新書の形で世に問うとのこと。いまから、楽しみです。
さて、これからの食の未来についての展望としては、まずは、食事の軍隊化、画一化、簡易化、工業化は進んでいくだろう。いっぽう、各地域独自の味や風味や品種は消されていく。
そんな悲観的な未来像に対して、「縁食」という概念を使って、食の未来の明るい可能性について考えてみたい。
まずは、各地域の味を守り発展させていく。そのために、地域の味を守る場所、ある種の公共食堂的な存在を構想する。そんななか、静岡県南伊豆の大衆食堂「いときち」の活動は参考になるだろう。
最後に、東京新聞2014年10月8日付けの朝刊の「筆洗」で紹介されたドキュメンタリー映画『聖者たちの食卓』。そこで描かれているのはシク教の聖地「黄金寺院」で、日々、十万人分!もの食事が用意されている、光景だ。カースト制の厳しいインドにあって、シク教はカーストなどあり得ないと教える。その教えの象徴が何百年も受け継がれて来たランガルと呼ばれる無料の食堂なんだそうだ。
こうした、社会に開かれた公共食堂のさまざまな可能性こそが、食の未来に光を投げかけることになるだろう。
■まとめ
21世紀。この世界はさまざまな課題に直面し、人類はなかなか明るい未来を構想できない局面に立たされている。
そんな状況のなかで、理想的な食の未来を実現するために、具体的にどういうアクションが必要になるのだろう。そう簡単なことではないのは、誰もが知っている。
科学が万能である時代は終ったけれども、だからといって、これまでの人類の営々と築き上げてきた文明を手放すわけにはいかない、私たちの現在において、藤原先生のような、物静かな語り口のなかに、研究者としての誠実と情熱を滲ませた姿に、食の未来の希望を持てた、そんな夜でした。